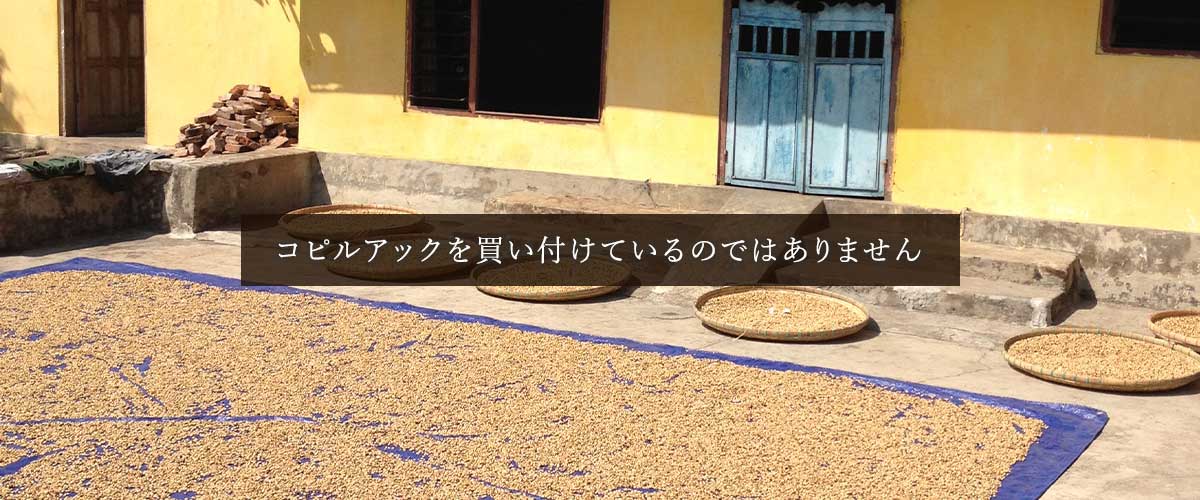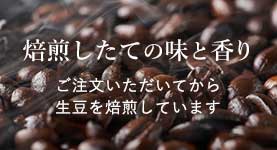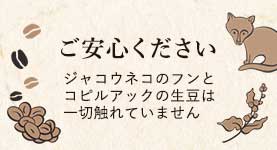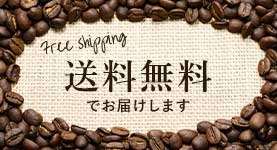ご注文から出荷までの日数について
ご注文から出荷までの日数について
Koki’s Kopi Luwakではフレッシュなコピルアックをお届けするため、
ご注文をいただいてからコピルアック生豆を焙煎しております。
-
ご注文
7月8日(火)午後6:00までに
-
焙煎予定日
7月9日(水)
-
出荷予定日
7月9日(水)
焙煎日、出荷日が1~2日前後することがございます。
アイスコーヒーはご注文後5営業日以内に出荷いたします。
配達日は最短で出荷日の翌日、地域によっては翌々日になります。
お知らせ
- 2022/01/01コピルアックアイスコーヒーの在庫が少なくなっております。品切れになる可能性もございます。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
- 2021/11/08Koki's Kopi luwakのショッピングサイトをリニューアルいたしました
おすすめ商品
Koki's Kopi Luwak Arabica/コピルアック アラビカ
¥3,300(税込) ~
Koki's Kopi Luwak Robusta/コピルアック ロブスタ
¥3,090(税込) ~
Koki's Kopi Luwak Arabica Gift/コピルアック アラビカ ギフト包装
¥3,510(税込) ~
Koki's Kopi Luwak Robusta Gift/コピルアック ロブスタ ギフト包装
¥3,300(税込) ~
Koki's Kopi Luwak/コピルアック瓶セット(アラビカ50g、ロブスタ50g)
¥6,080(税込)
Koki's Kopi Luwak/コピルアック ギフト包装 瓶セット(アラビカ50g、ロブスタ50g)
¥6,290(税込)
Koki's Kopi Luwak/コピルアック ギフトボックス瓶セット(アラビカ50g×2個、ロブスタ50g×2個)
¥12,360(税込)
Koki's Kopi Luwak /コピルアック ギフトボックス袋セット(アラビカ100g×1袋、ロブスタ100g×1袋)
¥10,100(税込)
Koki's Kopi Luwak アイスコーヒー ギフトボックス(2本入り)
¥6,850(税込)
Koki's Kopi Luwak アイスコーヒー(1本入り)
¥3,850(税込)
Koki's Kopi Luwak アイスコーヒー ギフトラッピング(1本入り)*現在在庫切れとなっております。
¥3,850(税込)
Koki's Kopi Luwak リキュール(2本入り) *現在在庫切れとなっております。
¥9,900(税込)